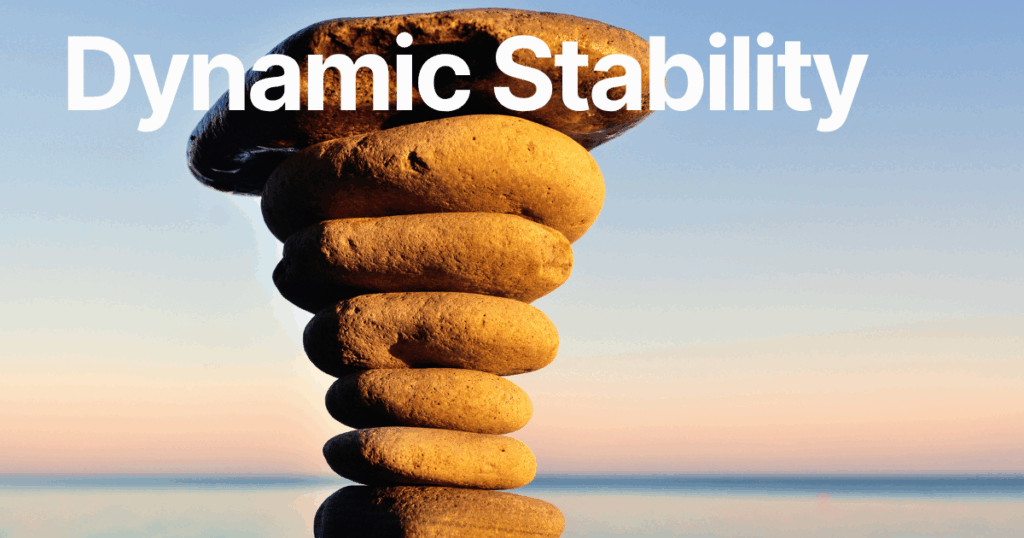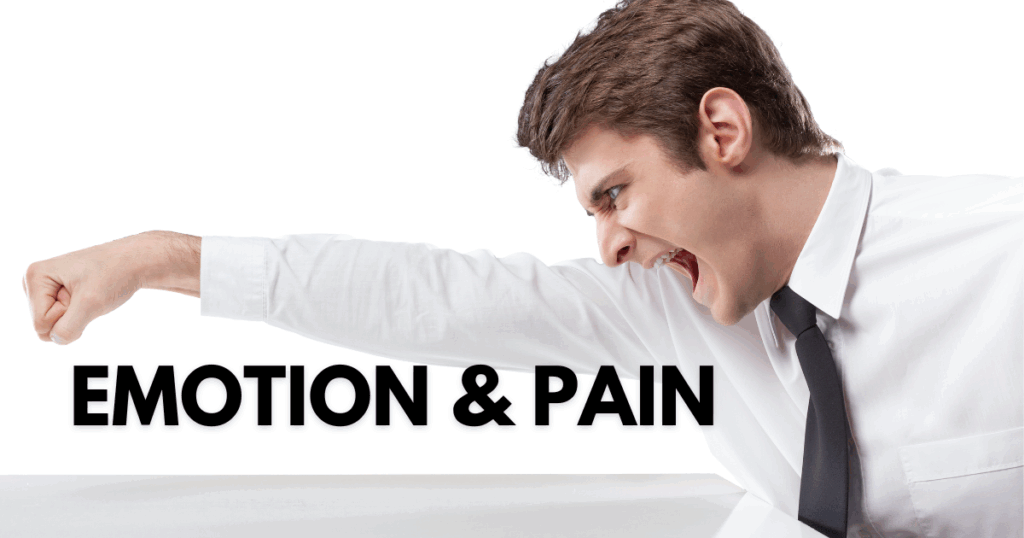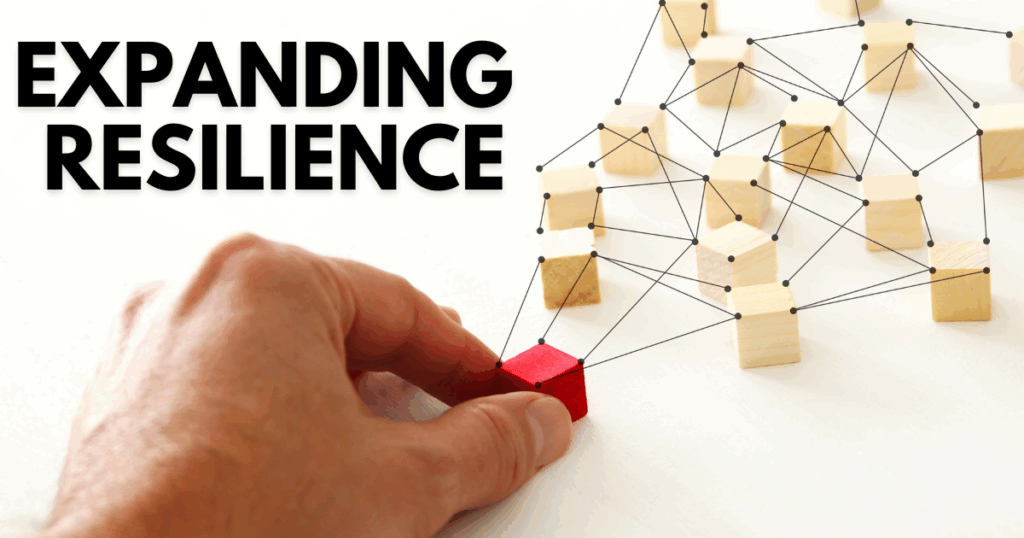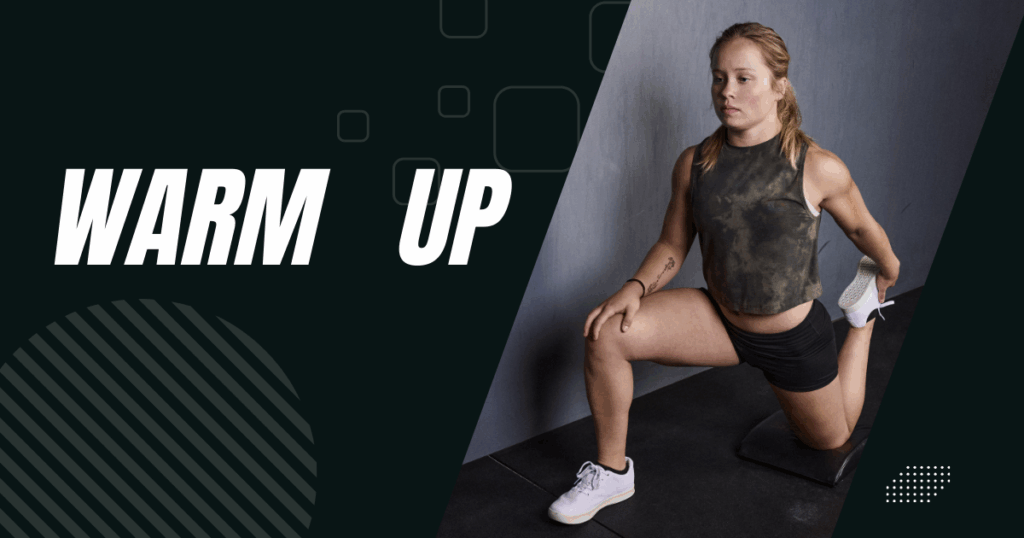2025年– date –
-

40〜60代の今こそ知りたい。“健康寿命”をのばす生き方とは?
40代を過ぎると、・疲れが抜けにくくなる・以前より体がこわばる・ちょっとした段差が気になるそんな“体の変化”を実感する方も増えてきます。 まだまだ若い気持ちでいるのに、じわりと訪れる変化。「このままの体で、私は何歳まで元気に動けるんだろう…?... -

横隔膜の“バキューム”で投げる
軸足股関節の引き込み→ 骨盤の前方移動→ 横隔膜のバキュームが立ち上がる→ 背中へとウェーブが伝わる→ ウェーブが胸郭の捩れへと上向きに伝搬する→ 胸郭の捩れがそのまま腕へ“乗り込む”ように流れる→ テークバックは「作る」のではなく“起こる” 腕は “振る... -

野球やスポーツ動作で重要なダイナミックスタビライゼーション
しなやかに力を伝える動き作り:ダイナミックスタビライゼーションを活性化して肘を守る体を作る ダイナミックスタビライゼーションとは? 野球の投球やバッティングなど、スポーツの動きで大切なのが「関節の安定化」です。ただ筋トレをするだけでなく、... -

痛みは動機に反応する:感情と身体の深いつながり
はじめに 「痛み」と聞くと、どこかをぶつけた、筋肉を使いすぎた、というような身体の損傷を連想する人が多いかもしれません。しかし、実は私たちの感情や動機が、痛みの感じ方に大きな影響を与えているということをご存じでしょうか? たとえば同じ家事... -

癖を超える身体:フェルデンクライス・メソッド
はじめに 「なんとなく動きが硬い」「同じところばかり疲れる」「姿勢がいつも崩れてしまう」――そうした悩みの背景には、**無意識の“動きの癖”**が潜んでいることがよくあります。 この癖を「矯正」するのではなく、やさしく気づき、選択肢を広げ、自発的... -

「動きの癖」から自由になる:身体的レジリエンスを育てるという考え方
はじめに 私たちは日々、無意識のうちに特定の「動きの癖」のなかで身体を使っています。それらの癖は、あるときは役立ち、あるときは制限となります。 フェルデンクライスメソッド(や他の身体技法でも)では、そうした癖に気づき、より自由で適応的な動... -

【高校野球】ピッチャーにおすすめ!インディアンクラブエクササイズ
ピッチャーの肩のケガ予防・フォーム改善に役立つツール、それが「インディアンクラブ」。ここでは、効果・メリット・注意点を高校野球向けにわかりやすく解説します! インディアンクラブとは? 木製またはプラスチック製のクラブ(バットに似た形)を使... -

“感覚を起こしてから動く”──神経を整える再学習型ウォームアップのすすめ
はじめに:温めるだけでは足りない 一般的なウォームアップは「体温を上げる」「筋肉を動かす」ことを目的としていますが、 神経の再学習や誤差修正が必要な状態では、それだけでは不十分です。 特に、 小脳機能の誤差学習が弱っている 視覚や前庭との統合... -

感覚のズレが動作を狂わせる──空間感覚と神経系の再統合
感覚のズレを作るのは視覚だけではない "視線がブレる" → "視覚トレーニングをしよう" という図式がありますが、実際には、視覚そのものだけでなく、 **後頭下筋群・顎関節・足底・三半規管などの“感覚受容器”**が、 前庭神経核〜小脳〜中脳〜大脳といった... -

慢性痛は“神経の迷子”かも!
はじめに:原因の見えない“痛み”の正体 筋肉をほぐしても、関節を調整しても、なぜかぶり返す痛み。 「慢性痛」の多くは、筋や骨だけでなく、神経系の“過緊張ループ”によって引き起こされている可能性があります。 そのループの出発点として近年注目されて...
-1024x479.png)