目次
はじめに
「適応的最適解(adaptive optimal solution)」という考え方について、最近特に重要だと再認識している。
これは単なるフォームや技術の話ではなく、その場の状況に応じて“今”自分にとって最も適した動き・判断を選ぶ能力のこと。
「適応的最適解」って
「適応的最適解」とは、
その時、その場、その状況に一番合った動きや判断のことです。
野球では、こんな場面で必要になります。
- ピッチャーがいつもと違うテンポで投げてくる
- グラウンドがぬかるんでいてスパイクが滑る
- 自分の体調が万全じゃない
- 相手打者のクセがいつもと違う
こういう時に「いつも通りのフォーム」だけにこだわっていると、かえって動きがうまくいかなくなります。
だから大切なのは、
状況に合わせて、自分の動きを少しずつ変えていく力
これが「適応的最適解」を出すということです。
「決まった型」と「適応」
- フォームや動作の「型」そのものは否定しない。
→ 土台・基準としては必要。 - しかし実戦では、相手や場面が常に異なる。
→ 同じ型を機械のように再現するだけでは、対応しきれない。
型はスタートラインであって、答えではない。
答えは「その場で探す」もの。
指導の中で意識していること
- 技術を「覚えさせる」のではなく、「動きの引き出しを増やす」
- 失敗を否定せず、どう修正していくかを見せる
- 適応力=“考える力+動きの微調整能力”と定義している
まとめ
適応的最適解を出せる選手は、
- 故障リスクが低い
- パフォーマンスが安定する
- 試合に強い(メンタルも含めて)
いわゆる「うまい選手」と「すごい選手」の違いはここにある気がしている。
引き続き、型と自由、制御と開放のバランスを考えながら、選手の動きを観ていきたい。
参考図書:『エコロジカル・トレーニングに関する思想的研究』
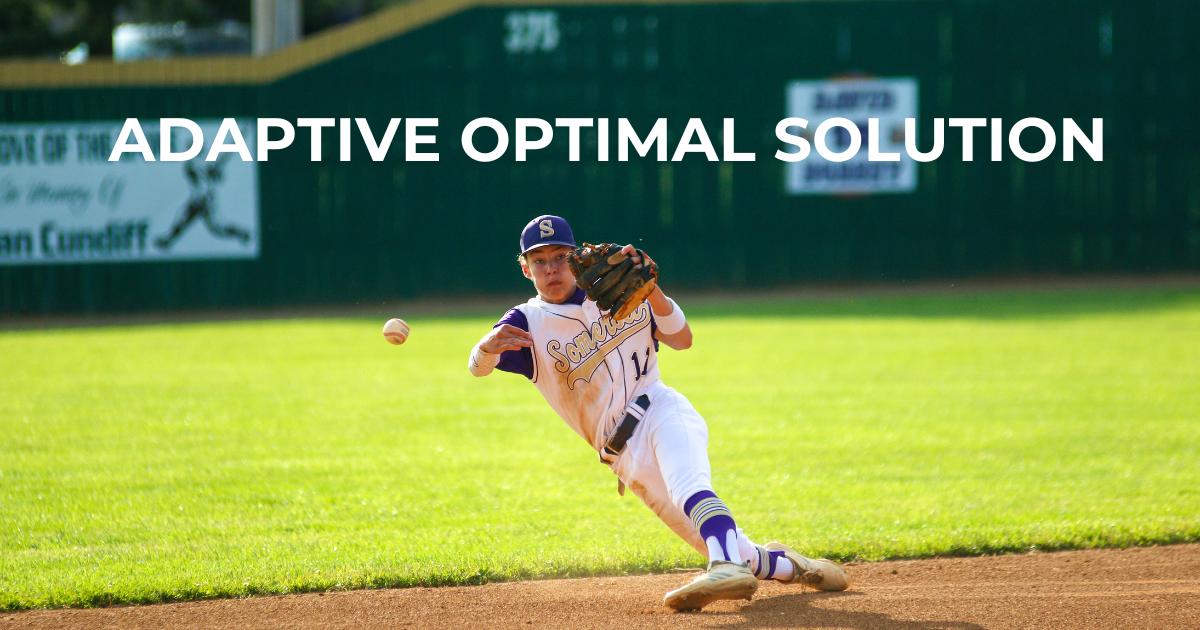
コメント