野球選手の繰り返す捻挫から考える足部安定性
はじめに〜選手の“足の硬さ”から見えたこと
先日、普段関わっている高校野球部の選手のコンディションチェックをしていた時のこと。
ふと右足の外側(腓骨筋)に触れたとき、妙に張っているのが気になりました。本人に話を聞いてみると、「たまに軽くひねることがある」とのこと。大きな捻挫ではないけれど、内反を繰り返しているようでした。
気になって片足バランスを確認すると、明らかに右足のほうが不安定。また、足関節の背屈もやや制限されていました。
この選手は右投げのオーバーハンドピッチャー。右脚はワインドアップから体重移動へとつなげる“軸足”として極めて重要な役割を担っています。それだけに、「この足の不安定さは、パフォーマンスにも影響しているのでは?」と感じました。
腓骨筋とは?何をしている筋肉?
腓骨筋(長腓骨筋・短腓骨筋)は、ふくらはぎの外側に位置し、足関節を外反(外返し)・底屈(つま先を下げる)させる筋肉です。
しかし、それだけではありません。
◾ 腓骨筋の主な役割
- 足関節の外側安定化
- 内反捻挫を防ぐ防御機構
- 横アーチの保持(長腓骨筋)
- 片足立ち時のバランス制御
- 歩行・走行・ジャンプ動作における足部のコントロール
つまり、腓骨筋は単なる「外側の補助筋」ではなく、足部と下肢全体の安定性を支える中核的な筋肉なのです。
腓骨筋の働きをチェックする4つのポイント
1. 片足立ちバランス(開眼 vs 閉眼)
この評価では、視覚情報と固有感覚のどちらに依存しているかが見えてきます。
- 開眼(目を開けた状態):視覚・前庭・足関節の固有受容器を使った全体的なバランス制御
- 閉眼(目を閉じる):視覚を遮断することで、固有感覚の精度や腓骨筋の反応が浮き彫りに
▶ 注目ポイント:
- 開眼では安定 → 閉眼で不安定:視覚依存型であり、腓骨筋や足部感覚の低下が疑われる
- 閉眼時の左右差が大きい:患側の固有感覚・腓骨筋の働きに問題がある可能性
裸足で行うと足裏からの情報も確認でき、より感覚的な評価がしやすくなります。
✅ 2. 片足スクワット
- 足部が内側に崩れる
- 膝が内側に入る(ニーイン)
- → 腓骨筋と後脛骨筋の働きが弱く、足部アーチや外側バランスを保てていない証拠
✅ 3. チューブを使った外反抵抗テスト
- ゴムバンドで外反方向に抵抗をかけて足首を動かしてもらう
- 筋力だけでなく、反応速度・動きの滑らかさがポイント
- ワンテンポ遅れる、すぐ疲れる、外側に痛みが出る場合は注意
✅ 4. 足関節背屈の可動域チェック
- 背屈制限があると、腓骨筋が代償的に働きすぎる傾向に
- 特に、距骨の前方滑りやアキレス腱周囲の硬さが関与しているケースも多い
腓骨筋の機能低下が疑われる兆候
- 片足立ちで肩が上がる・呼吸が浅い(全身で固めてバランスを取っている)
- 捻挫歴がある足側のみ外側の張りや痛みが出る
- ランニングやジャンプ後に足の外側が疲れやすい
- 投球・ステップ時に「足を信用しきれていない」感覚を訴える
こうした反応がある場合は、単なる筋力の問題だけでなく、神経的な再教育・感覚の質にも目を向ける必要があります。
まとめ
腓骨筋は、パフォーマンスを支える“縁の下の力持ち”です。
とくに野球のように片足での支持・回旋・踏み込みが求められる競技では、腓骨筋の機能不全がパフォーマンスの低下やケガの再発につながりかねません。
足の外側が硬い、片足バランスに差がある、捻挫歴がある――
そんなときには、「腓骨筋の状態」をチェックする価値が大いにあると感じています。
おわりに
選手のちょっとした「違和感」や「クセ」を見逃さず、丁寧に観察することが、ケガの予防とパフォーマンスの伸びにつながります。
腓骨筋という小さな筋肉に目を向けることで、身体全体の安定性や自信を支える土台作りができるかもしれません。
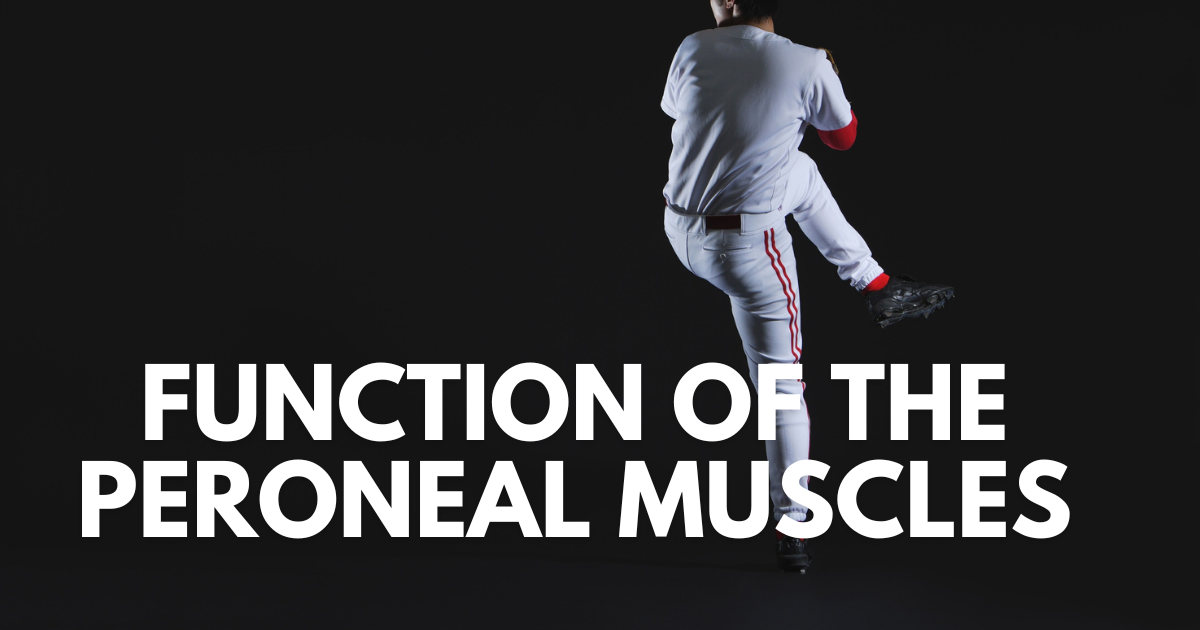
コメント